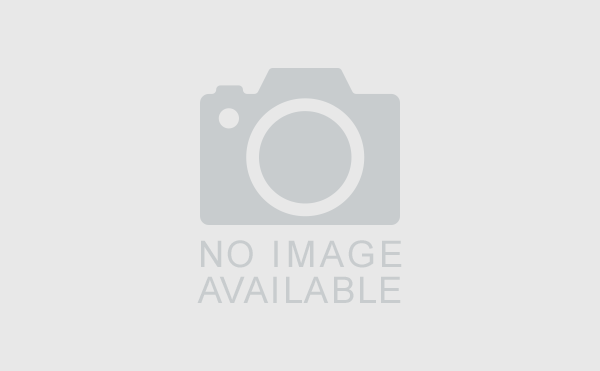なぜ都民は都心に住めないのか。

ウィーン7区。ほぼ6階建てに統一されている。
かなり以前チェコ人の通訳、パヴェル君と話していたら「東京というとテレビで通勤ラッシュを見たことがある」、と尻押しの場面を手振りで示しながら笑われたことがある。そのときはボクも笑って済ました。でもこれは本当は天下の笑い者なのだ。東京都民が、笑われて当たり前。
なぜ通勤通学ラッシュがあるかというと、都民が都心に住んでいないからだ。なぜ都心に住めないかというと、都心に住宅がもてないからだ。なぜ都心に住宅がもてないかというと、都心は「住宅区域」(一種住専、二種住専)とか「市街化調整区域」とか二重三重に規制がかかっていて、大部分は二階建て以下の住宅しか建てられないようになっているからだ。そういう地域では建ぺい率60%、容積率80%ぐらいになっていて、木造2階建てぐらいしか建てられない。
もしこれらの地域がウィーンやベルリンのように、5階建て~7階建てに限ると規制されていたなら(詳しい条例などは知らないが)、たとえば駒込の同一ブロックに居住できる都民の数は数倍、ないし数十倍になるであろう。山手線環状の内側に住める人は何万人も、いや何十万人も増える。学生、サラリーマン、さらに名門小中学校に通学する子供たちも、徒歩や自転車で移動できる。その上歌舞伎座とかオペラ劇場とかにも、せいぜいバスか電車で行けるようになる。(わざわざ国立劇場とか作って落語とか文楽とかの文化財保護をする必要はもともとないのであって、都民が夕食のあとに寄席に行く、という戦前の習慣が復活すればよいだけの話だ。)

ベルリン、シャルロッテンベルク。ほぼ6階に統一されている。
ベルリンやウィーンの市街地図を見たことのある人はすぐ分かることだが、市街図は建物のブロックで出来ている。つまり6~7階建ての集合住宅がいくつか集って、ひとつの街区を形成しており、その周りに道路がある。このブロックの真ん中は空間になっていて、よく言えば小公園、悪く言えばゴミ置き場などのスペースになっている。ボクはベルリンのこういう集合住宅(というかオフィスビル)の6階に入ったことがあるが、窓の外は緑豊かな街路樹の樹冠。中庭も明るくて、とても気持ちが良かった。もう一軒、こんどは鬱陶しい建物の6階まで昇ったことがある。街路樹がなくて、中庭はただの物置だった。こういう集合住宅は運営次第というところもある。とはいえ、やはり都心の集合住宅となると、陽当たりが悪いとか窓から窃視されるなどの不愉快なケースもありうる。それを補う意味で「シュレーバーガルテン」がある。つまり郊外の30坪程度のスペースを借りて、木造小屋を作り、野菜や果物、ワインなどを作る。週末の(金)(土)はそこに寝泊まりして、週日の息詰まるようなストレスを解消する、というものだ。東京でいえば小金井とか石神井公園あたりが、シュレーバーガルテンを設けるのに丁度良い。ところが実情は小金井や石神井公園は高級住宅地になっていて、とても週末に野良仕事なんかできない。逆に都心の駒込とか小石川あたりが、シュレーバーガルテンのような掘っ立て小屋の並ぶ「住宅地域」になっている。おかしいと思いませんか。

駒込付近。

中野駅北口。