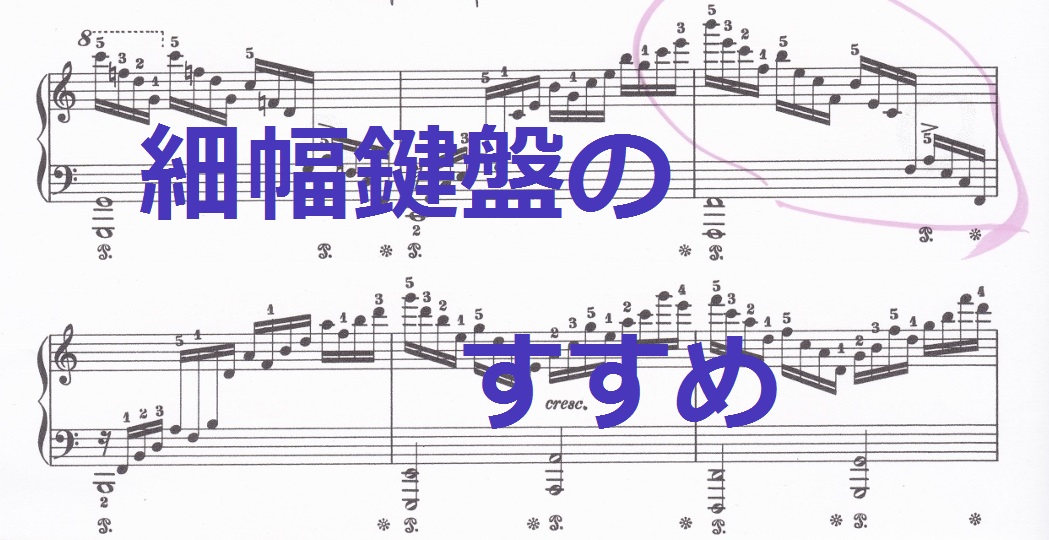菊五郎の鏡獅子
はじめて鏡獅子を見たのは、(妙な話だが)平櫛田中美術館だった。モデルは六代目菊五郎。
一橋大学小平分校に非常勤講師で行っていたころ、ぶらりと散歩していたら出くわした。なんだか知らないが、ただならぬ気魄があった。六代目菊五郎の名人芸と、田中の名人芸が相乗されているんだから、もう超絶的 (transzendent) である。(最初から脱線して恐縮だが、歌舞伎座三階の一隅に絵馬が展示してあった。観山、大観などなど。ものすごいセンスである。玉堂の描いた草の葉の、この世ならぬ緑色とか、呆然とするほかない。超絶が目の前にあって、その度合いを予感することはできても、しっかりついて行けない (nicht mitkommen können)。凡夫のもどかしさ。)
さて春興鏡獅子(5月13日公演)である。勇壮な「獅子の狂い」では、菊之助は鬣(たてがみ)を360度回転させていた。これは初めて。数十年前に団十郎の(?ウロ覚え)鏡獅子を見たが、そのときは、たてがみを左後方から右前方へと投げ出して、実質的には180度しか回転させてなかった。どちらが正調なのかは、分からない。
菊之助43歳、男盛り。獅子の精の荒技と、小姓弥生の女形と両方やれるぎりぎりのところなのだろうか? 弥生の衣装も、くっきりした紫を主調にしていて、数年前の淡い色調とは違っている。
誰かさんが東京五輪の開会式で、海老蔵の団十郎襲名披露をやることを夢見ていたらしいが、国立競技場で鬣(たてがみ)をぐるぐる回すだけでは(?)となってお終いではないだろうか。やはり江戸城本丸御殿から始まって、弥生の舞、胡蝶の精の舞、という段取りを踏んでから獅子の精が出なければ。嫡男丑之助の胡蝶の精はもちろん可愛い。いわばヨーロッパの Kittelzeit (スカート期)にあたる。男の子に女児の服装をさせる習慣。(これは中野京子の受け売りだが)男児は早世することが多いので、女児の服装をさせていた。その伝でゆくと、老人にも老婆の服装をさせると長生きするんじゃないか、と思われるが、そういう風習は寡聞にして知らない。ジジイは長生きしなくて結構ということらしい。
もう一人の胡蝶の精、亀三郎は板東彦三郎の息子にして楽善の孫であるらしい。家老渋井五右衛門(楽善)が退出するとき、用人関口十太夫(彦三郎)が両手を取ってやっと立ち上がらせ、襖を開けて退出させる、このあと孫の亀三郎が出てくる、なんともめでたい舞台を見たことを、あとで知った。
夜の部の「八陣守護城」について。ただひとつ雛衣(ひなぎぬ・雀右衛門)の琴は、望外の耳福だった。どれだけの難易度なのか等々は知らない。とにかく良く鳴っていた。箏曲では二度の不協和音も易々とメロディーに取り込んでいて、不思議な気持ちになる。むかし中村紘子が『ピアニストという蛮族がいる』のなかで、日本の管弦の貧弱さを嘆いていた、ように記憶するが(ウロ覚え)。どうして、歌舞伎座ではちゃんと響いている。武道館でエレキギターが響いたからといって、そっちが凄いわけではない。絵馬の額が、1000号の油絵に劣るわけではない。