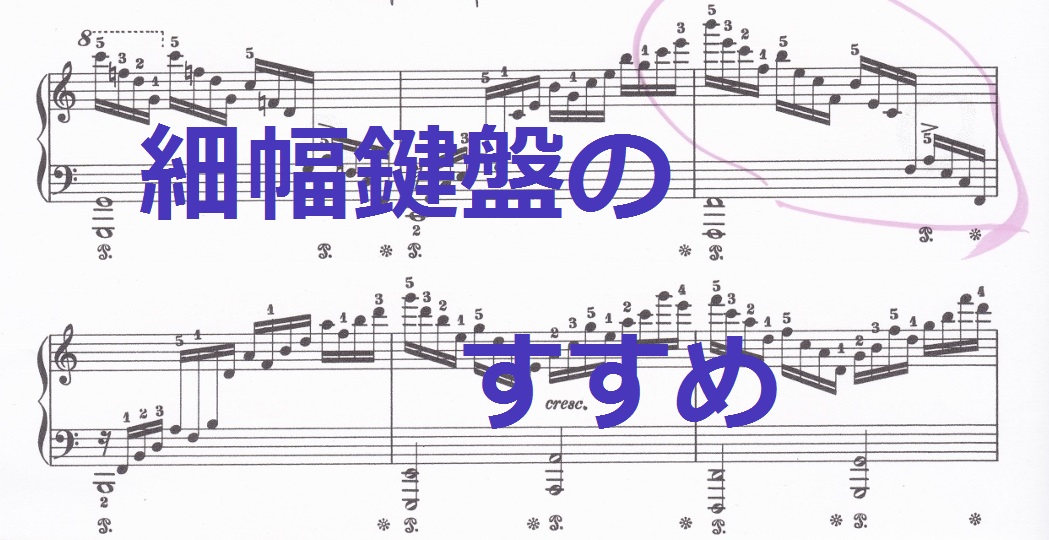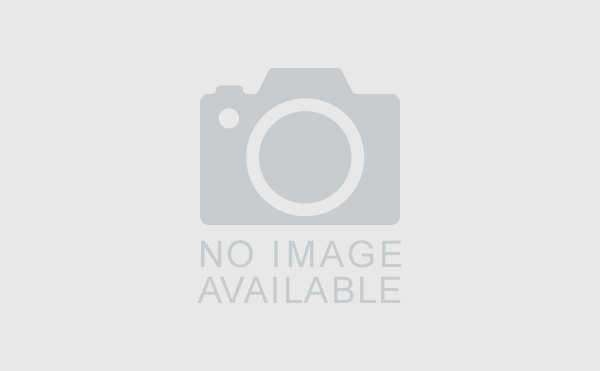ブラザーGU-131 の修理が終ります。
ほぼ半年ぶりに愛器ブラザー GU-131 に再会した。Piapit (千葉県印西市)の工房で修理してもらっていたのだ。

50年もののブラザー GU-131。以前から低音部の5つほどの音が、ズンというか濁った響きだった。試弾に来たDr. S.が「これは巻き線が弛んでいるんです」と診断。Piapitの渡辺順一代表に、弦の交換をお願いした。見積書では「弦バス交換、キーピン磨き、アクション総合調整、キー上面均し、運送(往復)」できわめてリーズナブルな費用だった。

低音部の巻き線は、ピカピカの銅線に交換されていた。この調音に時間がかかったわけである。
「ファイリングはどうしますか?」と、調律担当のTさんから電話があったので、「現物を見なければ」とPiapit にやってきた。

調律担当のTさん。( Piapit では複数の調律師たちがそれぞれの仕事をしている。)
試弾してみると、なるほど、中高音部や低音部で音色や強弱が違うので、ファイリングをお願いすることにした。(費用はやはりリーズナブル。)

「ただ見ただけではDS 6.0 が分からないから」と渡辺代表が、となりのカワイの標準鍵盤を向かい合わせに並べてみた。(上がブラザー GU-131。)

上記写真を撮影するためにカワイによじ登った渡辺代表。
渡辺代表は、拙宅( Kurze Finger スタジオ)にブラザー GU-131を引取りに来た際に、南西ドイツ・テレビのニュースのYoutube(3.8万回視聴)を見て「ホントだ、その通りだ」といたく賛同。Piapit に出入りする関係者や、通称「仙人」を始めとするピアノ・マニアたちに試弾させていたとのこと。「割と上級者の人たちが、弾きに来るね」。渡辺代表のような理解者、支援者が得られたことは心強い。

ブラザー GU-131との別れを惜しむ渡辺代表。
申し訳ありません。でも、ボクもこのピアノでマズルカを弾かねばならないのです。

招き猫の「もずく」ちゃん(雌)。ピアノの上に鎮座している。(ネーミングがぴったり。)
にゃンチュールをやったら、がつがつと。猫の舌はこんなに長かったっけ、と驚いた。
さて。工房に所狭しと並んでいる古今のピアノを撮影した。

プレイエル。前板がパリの地下鉄風になっている。

これもプレイエル。前肢ほか、お洒落なデザインだ。10年ほど前、パリでプレイエル・ホールを探したことがある。もう無くなっていた。栄枯盛衰、諸行無常。

イースタイン。これは中国のメーカーらしい。違った。Dr. S.によれば、Eastein は宇都宮に工場があった東京ピアノ工業(1949年~1973年)の製品。東京の East とスタインウェイの Stein を組み合わせた名前。BlüthnerのコピーのB型、ベーゼンドルファーのコピーのT型がある。Dr. S.によれば、知名度は低いがすぐれたピアノであって、出物があったらゲットしてオーバーホールすべきである。

ヘッセン。これは浜松のピアノ技研工業の製品。部品は中国製らしい。西尾社長は、ほかでもない、ウチのSteinbuhler-Walter社のDS5.5のコンソールを、大改造して「弾ける」ピアノにしてくれた大恩人である。Piapit には何でもある、というか、何があるか分からない。
*参考。
南西ドイツ・テレビのニュースYoutube。
Piapit
ピアノ技研工業
東京ピアノ工業