『クロイツァーの肖像』
昭和22年1月、日比谷公会堂。日本交響楽団の定期演奏会。シューマンのピアノ協奏曲の第2楽章の途中で停電になった。会場の明かりが点いて再会、また停電。それが10回ほど続くと、クロイツァーはたったひとりでソロ・パートにオーケストラ・パートを補いながら弾き始めた。闇の中で聴衆もオーケストラも唖然、呆然。ようやく電灯が点った瞬間、オーケストラが彼に和した。(203頁~)
有名なエピソードだそうだが、本書ではじめて知った。クロイツァー(1884年~1953年)が、ピアノ・パートを弾くだけで精一杯のピアニストでなく、指揮者であり、三幕もののオペラ『Marussia』(フル・スコアが遺品から発見された)の作曲者でもあって、本物の音楽芸術家であったことを覗わせる。指揮法はニキシュに、作曲はグラズノフに習う。ラフマニノフはペテルブルク音楽院の先輩、ショスタコーヴィチはグラズノフ先生の弟弟子。このあたりの周辺人物はキラ星のごとくである。
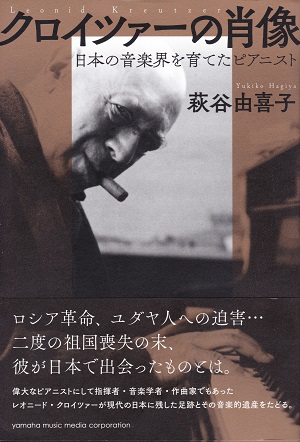 ユダヤ人にたいするポグロムを避けてドイツに移住、さらにナチスの弾圧を避けて日本に移住。曲折を経て(どこにでもあるが、とりわけ嫉妬や讒言は音楽界では顕著であるようだ)やっと安定した職に就き、織本豊子と結婚して1年8箇月、狭心症にて逝去。ロマノフのロシアでそのまま活躍できたら・・・と思うと、気の毒な生涯ではある。とはいえ、たとえばムージルは亡命の地ジュネーヴで、ほぼ忘れられたまま客死した。難解な文学が理解されにくいのに比べて、音楽が言語や国境を越えて理解され、支持されるのは、恵まれている。
ユダヤ人にたいするポグロムを避けてドイツに移住、さらにナチスの弾圧を避けて日本に移住。曲折を経て(どこにでもあるが、とりわけ嫉妬や讒言は音楽界では顕著であるようだ)やっと安定した職に就き、織本豊子と結婚して1年8箇月、狭心症にて逝去。ロマノフのロシアでそのまま活躍できたら・・・と思うと、気の毒な生涯ではある。とはいえ、たとえばムージルは亡命の地ジュネーヴで、ほぼ忘れられたまま客死した。難解な文学が理解されにくいのに比べて、音楽が言語や国境を越えて理解され、支持されるのは、恵まれている。
クロイツァーの演奏はどうだったのか。(まず聴かないことには、ただのファンののろけ話と変りがない。)Youtubeの「ラ・カンパネラ」を聴いた限りでは、高速スケールの粒だったパッセージが印象的だった。これだけでも超一流だったらしいと思える。弟子にして夫人のクロイツァー・豊子のマヅルカを数曲聴いた。香りがある。(クロイツァーが憑依している、と勝手に前提して聴いた。)1900年ごろには、まだリストの弟子の弟子、とか、ショパンの孫弟子とかがいて、一子相伝とか門外不出と(日本でなら)なりそうな秘伝が、細々と生き残っていたらしい。師アネッテ・エンポフがそのような接点になっていたのかどうかは不明ながら、なんというか、セピア色のショパンを聴く思いがした。
特筆すべきは、クロイツァーが細幅鍵盤を支持していたことだ。中田喜直が『音楽と人生』で引用しているように、クロイツァーは『芸術としてのピアノ演奏』のなかで、「狭い幅を持ったキー」について書いている。
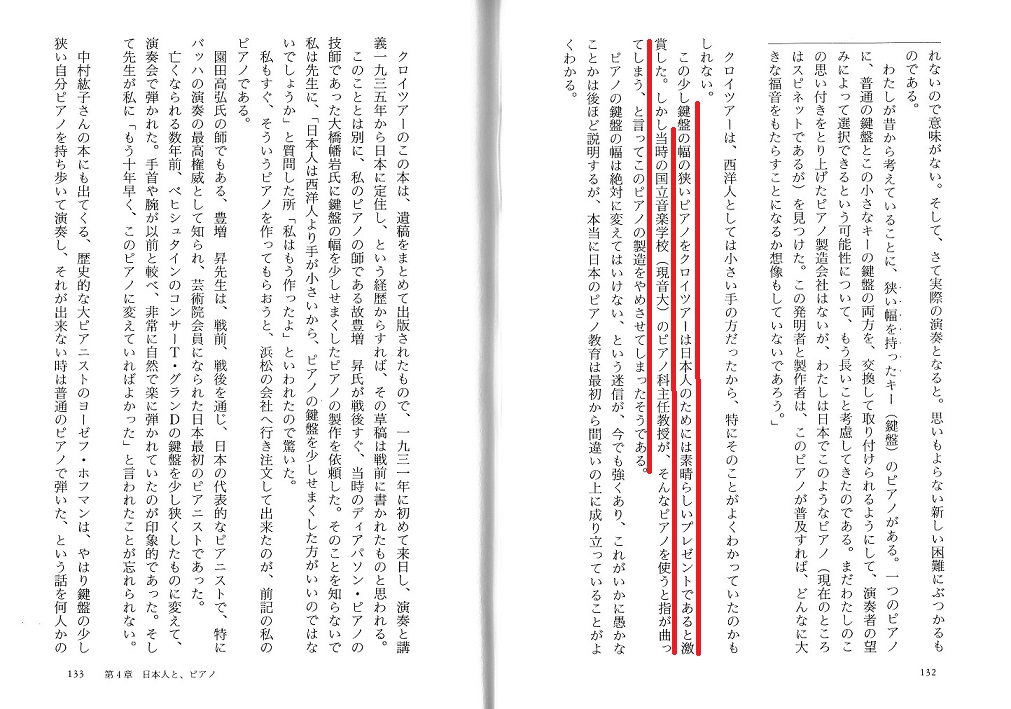 「西洋人としては小さい手」と中田喜直は書いているが、本書(『クロイツァーの肖像』)の裏表紙にある写真をみると、決して小さくはない。スパン24㎝前後はあったのではないか。(デスハンドは取らなかったのか? ショパンのデスマスクはなくとも、デスハンドは残っている。)われわれ日本人から見て、かなり大きい手であっても、現行の鍵盤幅は大きすぎるという傍証になるデータであると思われる。
「西洋人としては小さい手」と中田喜直は書いているが、本書(『クロイツァーの肖像』)の裏表紙にある写真をみると、決して小さくはない。スパン24㎝前後はあったのではないか。(デスハンドは取らなかったのか? ショパンのデスマスクはなくとも、デスハンドは残っている。)われわれ日本人から見て、かなり大きい手であっても、現行の鍵盤幅は大きすぎるという傍証になるデータであると思われる。
著者萩谷由貴子は、すでに「『蝶々夫人』と日露戦争」でみたように、周到な調査と絶妙な語り口で、至福の読書体験を演出してくれる。「バルトーク・ベーラ」と表記する見識と決断力にも敬意を表したい。クロイツァーの年譜、ディスコグラフィーもあり、労作でもある。あまり音楽に詳しくない読者は、小生のように、第三章「クロイツァーの来日」あたりから読み始めるとよいかもしれない。

