森岡実穂『オペラハウスから世界を見る』
やっと日本でも、本格的なオペラ評論家が現れた。たとえばその昔、約20年前のこと。某学術誌が「ドイツ音楽」特集を企画した。オペラ部門を依頼された某国立大学の某教授氏は、ドイツのオペラ雑誌2年分を読破して「こうなっています」とレポートした。もちろん彼は、そのうちの一作品も実際に見ていない。
ところが本書の著者森岡実穂氏はたとえば、リチャード・ジョーンズ演出のショスタコーヴィチ作曲『ムツェンスク郡のマクベス夫人』を、3つの劇場で観ている(2004年ロンドン、ロイヤル・オペラ・ハウス、2007年ミラノ・スカラ座、2009年新国立劇場)。さらに別の演出家たちによる同じ作品の上演も観ている(マルティン・クシェイによる2009年パリ・オペラ座、2006年アムステルダム公演は録画、ドミトリ・チャルニャコフによる2008年ライン・ドイツ・オペラ)。ただ「観ている」だけでなく、森岡氏は舞台を詳細に描写しながら、演出家の意図を探ってゆく。舞台装置、衣装、照明の担当者の来歴、傾向なども把握。「女性の孤独」、「女性は閉じ込められている」のだが、「最終的に彼女たちを閉じ込めているのは、自分の精神の内側に刷り込まれた、見えない囲いである。その見えない囲いが、いくつかの演出では〈見える〉形に変換されて提示されていた」(92頁)。舞台の写真も、きちんと版権処理した正式なものが提示されている(もっと多くてもよかった)。
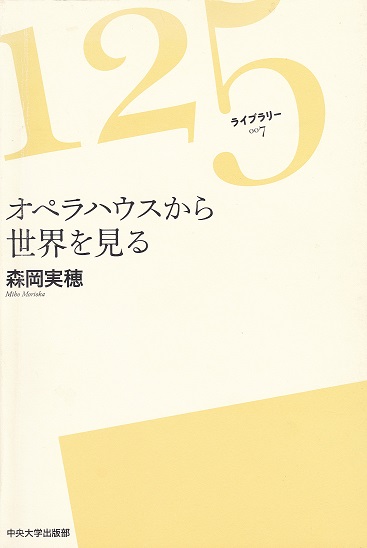 第4章の『蝶々夫人』は、もはや森岡氏の一八番(おはこ)と言ってよい。小川さくえ氏(『オリエンタリズムとジェンダー ー〈蝶々夫人〉の系譜』法政大学出版局)をはじめ、近年ジェンダー論やポストコロニアリズムの観点から論ずるものが幾つか出ているが、本書ではもはやそれらは周知の前提である。森岡氏はドイツ、フィンランドなど欧州各地の大小の劇場の『蝶々夫人』公演から、それぞれの演出家のユニークな解釈、演出意図を拾い出してゆく。たとえば格差社会の「貧困層」としての「蝶々夫人」、あるいは性的欲望を前面に出した「蝶々夫人」、あるいはケート夫人がスズキをビジネスライクに説得する姿から、傲慢な「アメリカ化」をあぶり出す演出、などなど。日本の劇場で2箇月に3日ほど、十年一日のごとき『蝶々夫人』を見せられているわれわれにとっては、上記のような公演ごと、演出家ごとに違う『蝶々夫人』が欧州であたりまえのように上演されていること自体、想像を絶しているのが現状ではないだろうか。
第4章の『蝶々夫人』は、もはや森岡氏の一八番(おはこ)と言ってよい。小川さくえ氏(『オリエンタリズムとジェンダー ー〈蝶々夫人〉の系譜』法政大学出版局)をはじめ、近年ジェンダー論やポストコロニアリズムの観点から論ずるものが幾つか出ているが、本書ではもはやそれらは周知の前提である。森岡氏はドイツ、フィンランドなど欧州各地の大小の劇場の『蝶々夫人』公演から、それぞれの演出家のユニークな解釈、演出意図を拾い出してゆく。たとえば格差社会の「貧困層」としての「蝶々夫人」、あるいは性的欲望を前面に出した「蝶々夫人」、あるいはケート夫人がスズキをビジネスライクに説得する姿から、傲慢な「アメリカ化」をあぶり出す演出、などなど。日本の劇場で2箇月に3日ほど、十年一日のごとき『蝶々夫人』を見せられているわれわれにとっては、上記のような公演ごと、演出家ごとに違う『蝶々夫人』が欧州であたりまえのように上演されていること自体、想像を絶しているのが現状ではないだろうか。
9.11以降「私たちは戦争の時代に生きている」(3頁)ことが、たまに日本海に「飛翔体」が落ちる程度、難民を年間に一ケタ程度受け入れている日本で、共通の認識になっているかどうか疑わしい。トロイ戦役を背景にする戯曲、オペラは膨大にあるが、『エレクトラ』(R. シュトラウス)、『トロイ人』(ベルリオーズ)のいくつかの公演は、アメリカのイラク侵攻、アフガニスタン内戦などを踏まえた、リアルな舞台となっているらしい。(えーと、疲れてきたので詳述できません。本書を読むべし。)巻末には詳しい年表が付いているが、ヨーロッパの個々のオペラ公演がこれらの事象に対応していることを印象づけるものだ。さて日本では。江戸時代という「300年間のビーダーマイアー期」がまだ尾底骨に残っている日本人には、時代に即応した舞台芸術はなじまないのだろうか? (昔は「サンデー志ん朝」という、毒気をはらんだTV番組もあったのだけれど。なお、歌舞伎座など「千年一日」を確認して安堵する施設は、それなりにあってよいと思っている。)
特筆すべきは森岡氏が、単一のイデオロギーに縛られずに、それぞれの舞台に接して瞬時に思考の枠組みを把握し、それに対応していることである(単一イデオロギーというのは、ボクは精神的怠惰だと思っている)。抽斗の多様さ、柔軟な対応力、そして信じられないほどの活動力、記憶力。森岡氏という希有な存在は、もっと評価されてよい。
最後に装丁について。松田行正氏の装丁は、『ムージル・エッセンス』(中央大学出版部)で素晴らしい冴えを見せたのだけれど。今回は中央大学「125ライブラリー」という箍(たが)が嵌められたためか、いかにもゼミの副読本みたいな、控え目なものになってしまった。これは出来ることならカラー写真を多用するなど、内容に見合った、素敵なものにして欲しかった。

